
とどかないものに手をさしだしているときの姿が
いちばん美しいのではないかと思う。

とどかないものに手をさしだしているときの姿が
いちばん美しいのではないかと思う。

喜んだり、悲しんだり。空をあおいだり、うつむいたり。
ひとにはひとのいろんな表情があるように、木には木のいろんな表情がある。
いまの機嫌はどんなですか。
たとえばそう聞いてみたとしても、すました顔でかわされそうだ。
若いもの、年老いたもの。
いろんな枝がひとつの木のなかに等しく在り、ぱやんぱやんとゆれている。

図面はいつも、このペンテルの0.5mmのシャーペンに、やはりペンテルAinSTEINの0.5mmのBの芯を入れて、ほとんど全部の線を描く。それはいろんないろんな芯の種類や太さや濃さを試したうえで結局最後まで残った組み合わせで、ある意味ではごくごく普通の、あたりまえの組み合わせであったりもする。
細かな文字を描く時には0.3mmの2Bを、地面のハッチングを描く時には0.9mmのBをまじえることもあるけれど、基本的にはほとんどのものを0.5mmのBをつかって描くから、このシャーペンを手に持つと図面を描いていない時でもなんだか調子がいい。
そんなわけで、今年からは手帳に何かを書き留めるときに使うペンも、いままで使っていたブルーブラックのインクペンからこの0.5mmのシャーペンに替えた。
あれはいったい、いつのことだったのだろうか。
ここ数年の手帳をいくつか見返してみたけれど、まったくどこにも見当たらないくらい遠くに遠くに遠ざかってしまった過去のありふれたある日の夜遅く、あんまり行かない街でたまたま入った地下の大衆酒場で、隣の席に座った常連さんが少し前まで手書きで施工図を描くことを仕事にしていたひとだった。
自分が手描きで図面を描いているのだということをちょっとだけそのひとに話をすると、そのひとはまっさきに「何ミリの芯で描いてんの?」と言った。芯の太さを聞いてくるひとなんてはじめてだったから、自分はすっかりうれしくなって「0.5のBです」と答えた。それでほとんど全部を描いています、と。
するとその施工図屋さんはニヤリと笑って「まだまだだなあ。」と言って、ゴクリと焼酎を飲んだ。
「全部、0.9で描かなきゃ。施工図ってのはさあ、ものをつくってるひとたちが現場でパッと見やすいように描かなきゃならないわけ。0.5じゃ薄すぎるんだよな。」
「でも、たとえば、図面の上に文字を描く時の引き出し線は、0.9だと太すぎて逆に見づらくないですか。自分は引き出し線は0.5か、縮尺によっては0.3で描いてるんですが。」
そんなふうに聞くと、そのひとは「引き出し線こそ濃く太く描かないとダメだよ。」と間髪をいれずに言った。「だってさあ、引き出し線ていうのは図面から文字を『引き出す』んだぜ。大工さんや職人さんに伝えたい言葉を図面の中からグイッと引っ張り出す線なわけ。だから、引き出し線こそ、か細い線なんかじゃなくて、グッと太い線で描かないと伝わんないんだよな。」
あれはやっぱりいつのことだったのだろう。
酔いのまわった頭にサーっと静かな波が押し寄せたあの晩は、何度探してもやっぱり手帳の中には見つからず、その日の地下の焼酎酒場にもそれ以来行くことが出来ていない。

ひとつ前に描いたものよりも、少しだけ丁寧に。
ひとつ前に描いたものよりも、少しだけ手間をかけて。
そうやってほんのわずかな少しをひとつずつ足していくと、前よりもなんだかちょっと、良い図面が描けたような気がしてくる。
良い図面が描けると、気持ちがいい。半透明の紙の上に、さーっと晴れ間がひらけてきて、気持ちがさらさらと澄んでくる。図面がうまく描けたなあと思ったら、ふーっと休んで、息をついて。次はここからあと少し、工夫をこらして、手間をかけて。そうしてもうほんの一寸ばかり、うまく描けるようになれたらいい。
自分の手で、一歩ずつ、ひとつひとつ。地べたに足をくっつけながら、ゆっくりと歩いていくように、描いていけたらいいなと思う。
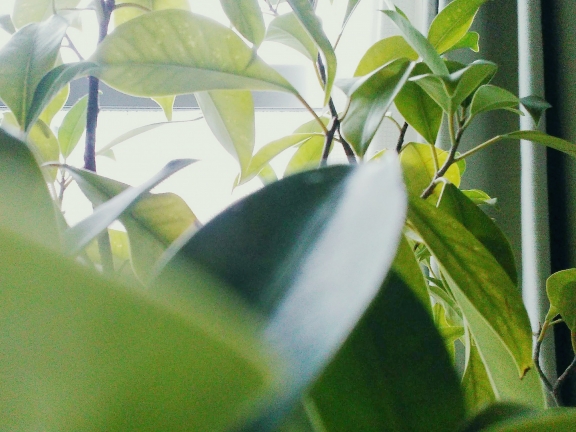
家のガジュマルは毎年同じようなペースでいくつかの葉っぱを落と
そろそろきみも中年だねえ、なんて言ってみたくもなるけれど、ガ
落ちていく葉っぱはすこし乾いて黄色くなって下を向き、生まれて
このみずみずしさに道を譲るために、古い葉っぱは自分の
そろそろいい加減、もうひとつ大きな鉢にうつしてあげねばとも思
仕方なく、今朝も乾いた葉っぱをせっせと手にとって、それから鉢

雪の朝。凍りついたアスファルトの路面は山の道よりも滑るか
終着駅で停車中の電車に乗ると、車両の端から作業服を着たひとが
小脇に抱えられたものはよく見ると小さな古い木の椅子で、年季の入ったその脚には白い手書きの文字で何かの言葉が書
そのひとはたぶん、中吊り広告の張り替えをしに来たひとで、
あの古びた脚には、白い文字で、いったいどんな言葉が書かれているのだ

「山の上でこんな話ができるなんて、うれしいなあ。」
年の瀬のよく晴れた日の午後。たまたま少しの間立ち寄っただけなのに、自分のへたくそな話にそんなふうに言っていただき、とってもうれしかったです。それにやっぱりその峠の小屋のひとたちは、おふたりとも自分の家や自分の小屋を自分の手でたてたひとたちで、そのことにもすーっと静かな感動を覚えながら古い木のテーブルの前に座っていました。
にこにこと笑顔で話をしてくださる小屋のひとたちのうしろには、そのひとたちとは直接のつながりはないかもしれないたくさんのひとの姿が、小さな窓から差し込む光に透けるようにしてぼんやりと見えているような感じがしました。
えんぴつの木を彫った手づくりのふくろう、大事にします。ご主人の顔はどことなくそのふくろうに似ていました。

思っていたよりも雪の少ない峠の道を、落ち葉を踏みながら少しずつあがっていく。
一歩一歩ゆっくりと登るごとに、手前の山のうしろにかくれていた別の山の姿がちょっとずつ見えてくる。もう少し道を登ると、ふたつの山が連なって、ひとつの稜線が生まれる。そうしてしばらく歩いていくと、今度はその稜線のうしろにまた別の山々の稜線がゆるやかに重なって、ひとつひとつ微妙に色合いや明るさの違ういくつもの蒼い層が視界の先にのびやかにひろがっていく。
奥秩父の山々のむこうに、真っ白に輝く八ヶ岳の峰々がすーっと立ちあがってくる。目の前の道の右手ではきのう歩いた稜線のうしろに、どーんと構えた富士の頂がぐんぐんと大きくなって天を衝く。振り返ると、一列にならんだ真っ白な南アルプスの手前に甲州の小さな山々が静かに手を繋ぎながら座っている。
ひとつとして似ているもののないそれぞれの山々が、ある時は連なり、ある時は重なりあって、大きなひろがりをつくっている。他の山から切り離されて独りで立っている山はどこにもない。もしそのように見える山があったとしても、それはもう少しこの道を登ったところから振り返って眺めてみれば、きっとまた違う見え方をしているのだろう。
ひとつの山は、他の山と連なって重なって、そうしてはじめて山になる。なんだかちょっと、ひとのようだなと思う。もし自分が今日この道を登ってこなかったら、そんなありふれたことにさえ、気がつかなかったのかもしれない。蒼く澄んだ稜線がいくつもの層になって空に透けている。
雪のつもった北斜面を西のほうから巻いていく。名前も知らない新しい山々のむこうに、いつか歩いた懐かしい小さな山々が見えてくるような感じがして思わず手を振って挨拶をしてしまいそうになる。林のむこうに見えなくなった蒼い峰々にもたくさんの感謝を伝えることができたら良いのになあと思う。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
