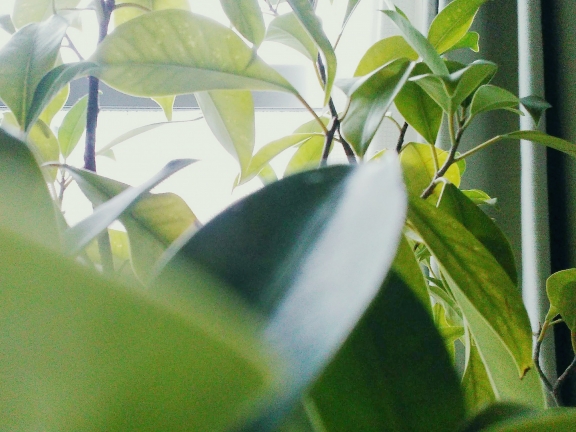
家のガジュマルは毎年同じようなペースでいくつかの葉っぱを落と
そろそろきみも中年だねえ、なんて言ってみたくもなるけれど、ガ
落ちていく葉っぱはすこし乾いて黄色くなって下を向き、生まれて
このみずみずしさに道を譲るために、古い葉っぱは自分の
そろそろいい加減、もうひとつ大きな鉢にうつしてあげねばとも思
仕方なく、今朝も乾いた葉っぱをせっせと手にとって、それから鉢
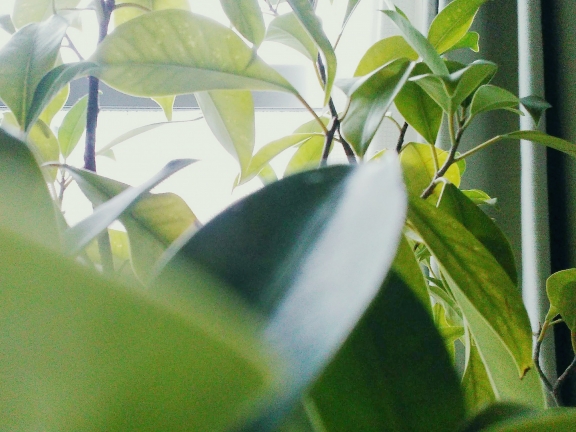
家のガジュマルは毎年同じようなペースでいくつかの葉っぱを落と
そろそろきみも中年だねえ、なんて言ってみたくもなるけれど、ガ
落ちていく葉っぱはすこし乾いて黄色くなって下を向き、生まれて
このみずみずしさに道を譲るために、古い葉っぱは自分の
そろそろいい加減、もうひとつ大きな鉢にうつしてあげねばとも思
仕方なく、今朝も乾いた葉っぱをせっせと手にとって、それから鉢

雪の朝。凍りついたアスファルトの路面は山の道よりも滑るか
終着駅で停車中の電車に乗ると、車両の端から作業服を着たひとが
小脇に抱えられたものはよく見ると小さな古い木の椅子で、年季の入ったその脚には白い手書きの文字で何かの言葉が書
そのひとはたぶん、中吊り広告の張り替えをしに来たひとで、
あの古びた脚には、白い文字で、いったいどんな言葉が書かれているのだ

「山の上でこんな話ができるなんて、うれしいなあ。」
年の瀬のよく晴れた日の午後。たまたま少しの間立ち寄っただけなのに、自分のへたくそな話にそんなふうに言っていただき、とってもうれしかったです。それにやっぱりその峠の小屋のひとたちは、おふたりとも自分の家や自分の小屋を自分の手でたてたひとたちで、そのことにもすーっと静かな感動を覚えながら古い木のテーブルの前に座っていました。
にこにこと笑顔で話をしてくださる小屋のひとたちのうしろには、そのひとたちとは直接のつながりはないかもしれないたくさんのひとの姿が、小さな窓から差し込む光に透けるようにしてぼんやりと見えているような感じがしました。
えんぴつの木を彫った手づくりのふくろう、大事にします。ご主人の顔はどことなくそのふくろうに似ていました。

思っていたよりも雪の少ない峠の道を、落ち葉を踏みながら少しずつあがっていく。
一歩一歩ゆっくりと登るごとに、手前の山のうしろにかくれていた別の山の姿がちょっとずつ見えてくる。もう少し道を登ると、ふたつの山が連なって、ひとつの稜線が生まれる。そうしてしばらく歩いていくと、今度はその稜線のうしろにまた別の山々の稜線がゆるやかに重なって、ひとつひとつ微妙に色合いや明るさの違ういくつもの蒼い層が視界の先にのびやかにひろがっていく。
奥秩父の山々のむこうに、真っ白に輝く八ヶ岳の峰々がすーっと立ちあがってくる。目の前の道の右手ではきのう歩いた稜線のうしろに、どーんと構えた富士の頂がぐんぐんと大きくなって天を衝く。振り返ると、一列にならんだ真っ白な南アルプスの手前に甲州の小さな山々が静かに手を繋ぎながら座っている。
ひとつとして似ているもののないそれぞれの山々が、ある時は連なり、ある時は重なりあって、大きなひろがりをつくっている。他の山から切り離されて独りで立っている山はどこにもない。もしそのように見える山があったとしても、それはもう少しこの道を登ったところから振り返って眺めてみれば、きっとまた違う見え方をしているのだろう。
ひとつの山は、他の山と連なって重なって、そうしてはじめて山になる。なんだかちょっと、ひとのようだなと思う。もし自分が今日この道を登ってこなかったら、そんなありふれたことにさえ、気がつかなかったのかもしれない。蒼く澄んだ稜線がいくつもの層になって空に透けている。
雪のつもった北斜面を西のほうから巻いていく。名前も知らない新しい山々のむこうに、いつか歩いた懐かしい小さな山々が見えてくるような感じがして思わず手を振って挨拶をしてしまいそうになる。林のむこうに見えなくなった蒼い峰々にもたくさんの感謝を伝えることができたら良いのになあと思う。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

「自分はただこの場所に、このようにして在れたら、それでいい。」
見え方とか受けとめられ方とか聞こえ方とか、そんなようなものの一切から遠く離れた素朴な場所で、ただ在り方だけを強く祈りながらじっと動かずに立っている。見上げると、そんな木がそこにある。

すぐれた屋根は、その土地が背中にかかえた小さな山々の稜線に、どこかとてもよく似ている。

いつも通る農園の、パイプで組まれた簡素な小屋の前にさしかかった時、ちょうど信号が赤に変わった。小屋の中を見ると、トマトやピーマンなんかの夏野菜が色とりどりに売られていたカゴの中身は、農園のひとたちが手作りしたたくあんと、それから白菜漬けだけになっている。
すっかり冬景色になった農園の前を発車して自転車を漕ぎはじめると、大きめの通りを1本渡ったあたりで、頭にかぶったニット帽に小さな何かがコンコンと打ちつけてくるのに気がついた。まだむこうの空は明るいのに。思わず天を仰ぐと、氷の粒がコツコツとひたいにぶつかりながら降ってくるのが目に入った。
でも、ちょっとくらいなら。呑気にそう思ってのんびり自転車を漕いでいくと、コンコンという音はみるみるうちにジャージャーという大きな音へと変わって、たくさんの氷の粒が視界をさえぎりはじめる。目の上のあたりに打ちつける小さな粒たちがなかなかに痛い。なにもこんなに寒い日に、氷まで降ってこなくても良いだろうに。。
今日の雲は南から北へと流れていたはずだから、このまま北へとまっすぐに走っていけばなんとかかんとか逃げ切れるかもしれない。古い商店街の脇をのびていく平坦な道を一目散に自転車を漕いで、北の小屋をめざした。

しばらくのあいだベランダに生えたヒエやらアワやらを早朝に必死に脱穀しに来ていたスズメたちも、冬至が近づくにつれてすっかり寝坊助さんになり、人間のほうが早く目を覚ますようになってきた。
この前の朝、遠い国のあるベース弾きのひとが亡くなって、彼の遺した半世紀ほども前の音楽たちを何度も再生した。そのなかのひとつに、あるグループのバックで彼がベースを弾いたものがあって、それは一般的には決して有名だったり評価されたりしたものではないのだけど、自分はどうにもその頃の彼らの音楽のうしろで低く鳴るベースとドラムの音が大好きで、地面の上から空を見上げて踊りだすようなその音を、やっぱりその朝も幾度かくりかえし聞いていた。
窓の外にはいつものように寝坊したスズメがやってきて、庇のうえにとまってガサゴソと何かをやっている。草のあたりにはいないから、どうやら今日は脱穀をしに来たわけではないらしい。
「チュンッ。チュンッ。」
しばらく聞き耳をたてていると、寝坊助の彼はスピーカーの中のベースの音にぴったりとリズムを合わせるかのようにして短く何度か鳴いた。そうしてそれから元気に羽ばたいて、よく晴れた冬の空をまた次のどこかへ飛んでいった。

はじめて入った古い小さな食堂で中華そばを注文して、丸椅子のうえから何の気なしに目の前を見あげると、壁の上のほうにA4くらいのサイズの紙が木枠の額に入れられて飾ってあるのが目に留まった。
その紙には地元の小学生が手書きしたらしいいくつかの言葉が、さっぱりとした綺麗な文字で描かれていて、この商店街のことをもっとみんなに知ってもらいたいこと、そのために商店街の古い歴史を調べていること、そのためのポスターをつくったのでそれをお店に貼ってほしいことなどが、丁寧な言葉づかいでしたためられていた。その額のすぐ下のところにはもうひとつ小さな紙が貼られていて、この食堂のすぐ前にある細い細い路地の来歴のようなことが、これまた小学生の手による丁寧な文字で書かれていた。
この路地のむこうには、むかし海のなかに鳥居が立っていて、路地に佇むとその鳥居が水面に浮かんでいるように見えたことから、この路地にはこれこれの名前がついたのだそうです。
概ねそんなようなことが書かれた小さな紙とその上の額を交互に見上げているうちに、アツアツの中華そばをお母さんが運んできてくれて、ふたつの紙の手前にもくもくと香ばしい湯気がたちのぼった。とびきりに美味しかったその食堂の中華そばの味わいは、壁に掛けられた木枠の額とそこに丁寧に手書きされた小学生の文字の感じにも似た素朴さがあって、その余韻を感じながらガラガラと引戸をあけて店の外にでた。
店の前の路地の先には新しい建物が建ちならび、その建物たちに遮られて路地の上から水面をのぞむことはもう出来なくなってしまっていたけれど、そのむこうにゆったりと横たわる海の上のどこかには、きっと今でも古びた鳥居がちょこんと簡素な佇まいで立っているんじゃないかなという気がした。

最近はじめて訪れた町で、それぞれの町の夕日に出くわすことが何度かあった。
山にかこまれた盆地にある平らな町、斜面にくっつくようにして立っている小さな町、やわらかな海をかかえた港の町。それぞれの町にはそれぞれに固有のかたちのようなものがあって、そうしたかたちをほんの束の間、夕日のおちていく前のひとときが空のむこうにくっきりと浮かびあがらせているようでもあった。
昼の空気に霞んでいた遠くの島や、雲のむこうにかくれていた向こうの山。あるいはそのまたむこうに横たわっていたおだやかな山脈。
きっとその町のひとたちはそうしたかたちに囲まれて、ずーっとむかしからその場所で暮らしてきたのだろう。真昼の時間には見えてこなかったそんなかたちのいくつかが、あっと息をのむ間もなく冷えた空気のむこうにふっと浮かんで、それから真っ暗な夜がしんしんと歩み寄ってきて、深い闇がそうしたかたちのひとつひとつをすっぽりとくまなく覆い隠していく。闇にかくされてしまう前のかたちを、ひとはなんとか自分の心にとどめようとする。
はじめて訪れた町で夕日を見ることができると、だからほんの少しだけ、その町のかくされた姿のようなものに親しむことが出来たような、なんだかそんな気分になることが出来るわけで、きっとそれは新参者のいだく幻影ではあるけれど、それはそれでひとつの町とひとりのひとの関係のあり方なのではないかと思ったりもする。
ひとが古いものを壊し、新しい建物をたて、山を削り、海を埋め立てても、それでもなおたいして変わることのないその町のかたちがあるとしたら、そのかたちに出会うことが叶うのは、あざやかな朝でも明るい真昼でもなく、暗い夜の訪れる前のほんのわずかな数分の間であったりもするのかもしれない。

「眺望が良い」ということの良さが自分なりに理解できるようになったのは比較的最近のことで、それまでは山や森はその内部に入りこんでいけるからこそ素晴らしいのだと感じていた。そんなふうにしてふらふらと内側を歩きまわることばかりを楽しんでいて、あれはいつ頃だっただろうか。あるとき、それほど都会から離れていない場所にある小さな山に登った時に、ふいに冬枯れの林のむこうに東京の街並みが霞んでみえたことがあった。
その山はたいして高い山ではなかったから、そこから見える街並みは、どこか高いところからそれを見下ろしているという感じはなく、その街と自分との間にたっぷりと大きな余白があって、その余白をはさんで遠くから水平に街を眺めている、という感じがあった。高さの違いがすくないぶん、距離の感覚が際立っていて、むこうの街と自分との間を低い光に真っ白く照らされた冬枯れの枝たちが一面におおいつくしていた。
そこから見えたむこうの街では、たぶんたくさんの誰かが今日もせわしなく仕事に追われたり、なにかを考え込んでみたり、あるいは自己を主張し合ったりしているのだろうと思われたのだけど、ついさっきまでその真っ只中に居た自分自身と、その街との間にある十分な余白、たっぷりとひらけた距離が、なにかそういった日々の重々しいあれこれを大らかにすいこんで、ふーっと軽い空気に変えて息をはきだしてくれているような、なんだかそんな明るい感じをその時の自分は覚えたのだった。
山や森のかたちをした大きな余白がふーっとゆっくり呼吸をするたびに、さっきまで肩に入っていた無駄な力がゆるゆるとほぐれて、ふんわりと軽やかな雰囲気に満たされていく。その息づかいをうっすらと身体に感じているうちに、むこうの街にいるひとたちのひとりひとりにまっさらな気持ちで素朴にむきあうことが出来るようにも思われて、なるほど眺望というものはつまりそんなようなわけで素晴らしいものなのかと、遅ればせながらその時はじめて気がつくことになったのだった。

それまであたりまえのように手にしていた何かを捨てて、あたりまえでない何かをはじめることは、簡単そうに見えて、なかなか結構むずかしい。あたりまえのように手にしていた何かを捨てるには動機がいるし、あたりまえでない何かをはじめるには、たとえそれがどんなに小さなことだったとしても、ある種の憧憬のようなものの力を借りる必要だって時にはあるのかもしれない。
おとといの夕方、山のむこうの遠くの町のあるひとから電話が鳴った。
そのひとが大工さんの力を借りながら自分の手でたてた山麓の小屋を最後に訪ねたのは、小屋のまわりの白樺林の斜面が一面の真っ白い雪におおわれはじめていた頃だから、ちょうど2年前の今頃で、そのときはまさかこんなにも長い間、その小屋やその町に行くことが出来なくなるなんて思ってもいなかった。
そのひとと会話をするのは相当ひさしぶりのことだったから、本当はこの2年の間のあれやこれやのよもやま話などを電話口で報告するべきだったのだろうけれど、そのひとにまず自分が伝えるべきことはただひとつ、この小屋のことなんじゃないかなと思って、この小屋でのあれこれを簡潔にお話しすることにした。
それまで使っていた事務所の場所を退去して、半年ほど前からこの小屋を使うようになったこと。ここが古い農小屋で、ここには水道も電気もガスもひかれていないこと。だから水と食料と蓄電池をいれたザックを担いで自宅からこの小屋に通っていること。片道1時間、寄り道をしながらひとりのんびりと自転車を漕いでくる道中が山の道のようで楽しいこと。冷房も暖房もないから、今は冬山に行く時の服装で仕事をしていること。蓄電池に繋いだ小さな裸電球の灯りの下で、いまこの電話にでていること。
だいたいそんなようなことを、電話のむこうのひとに手短にお伝えした。動機は特に言わなかったし、たぶん言う必要もないだろうと思った。ただ、そうしたことのすべてが、水も電気もガスもないどこか遠くの山の中を、のほほーんとひとりで歩いていくような気分とむすびついているような感じがすることぐらいは、きっと、なんとなく分かってもらえるんじゃないかなあ。
「おまえ。」
案の定、電話口のむこうの声がにやりと弾んで、そう言った。
「おまえ、それは、おれと同じじゃないか。」

山に行って、すこし前に歩いた山が見える。
そうすると、その山を歩かなかった時に見えていたものとは、また違ったなにかが見える。
それと同じようなことが、ひとが自分の手足を動かしてなにげなく暮らしている毎日の中にもたぶん確かにあって、だから少しでもたくさん手と足を動かして、暮らしていけたらと思う。
さっきノートにむかいながら、ふと思ったこと。

シラビソ、オオシラビソ、トウヒ、カラマツ。
しーんとした針葉樹の森にぐるりと周囲をかこまれた山の池は、ちょっとの音や小さな声がこだまして、ほんとうによく響く。
夕方、テントのそばの池のほとりに座っているとき、小屋のひとがなかなか現れない宿泊者のひとを探しに、池の反対側からこっちまで歩いてきた。どうやら宿泊予定のひとが途中の山でちょっと道に迷ってしまったとかで、小屋に着くのが遅れてしまっているらしい。心配そうな顔つきの小屋のひとはそのまま池のまわりを奥へと進んで、森の入口のあたりへと向かっていく。
「おーい、○○さんいますかー!?」
小屋のひとの大きな声がきーんと冷えた静かな池のまわりにこだまする。
「はーい!!」
もうじき日没を迎えようとする薄暗い森の見えないどこかから、女のひとの元気な声が返ってきて、それから間もなく、ほっとした顔をした小屋のひとと宿泊者のひとが、そろりそろりと池のところへ歩いてきた。

朝、1時間ばかり電車に乗って、はじめての駅におりて改札を通って外へと出たとき、道のむこうにくっきりと、ある山の大らかな稜線が見えた。
次々に車の通りすぎる大通りを歩いて駅から目的の場所へとむかう道すがら、その稜線は2階建ての家やビルの影にかくれてすっかり見えなくなってしまったのだけれど、目的の場所に着いたとき、畑のむこうにもう一度その山の稜線がぽかーんと大きく浮かんでいるのが見えた。
ずーっとむかしのある時にも、あの稜線をこの場所から見ていたひとがいたのだろう。そのひとはきっと地面の土を耕しながら、あの稜線を仰ぎ見ていたのだろう。なんだかそのことを忘れずにいようと思った。

上流から何度かのゆるい蛇行をくりかえした川は、ちょうどそのあたりでまっすぐに西から東へと流れの方向を変えて、その川に沿って両側にまっすぐな細い道がつづいている。南側にはケヤキ並木が、北側には大きな木々の生えた古い家が並んでいるから、東西の方角にだけ空がぬけている。
このまえのある日、いつもそうするように、その川に沿って西のほうへと歩いていって、それからしばらくして東のほうへとてくてくと歩いて戻ってきた。きーんと空気が冷えはじめた秋の夕暮れで、西の空にはムクドリの群れが羽ばたいて、東の空にはまん丸い月がぽかんとひとつ浮かんでいた。
ムクドリたちは西のほうへと飛び立ったかと思うと、ぐるりと旋回して、また同じ古い大きな木の上のほうへと戻ってくる。するとその木の中でヒヨドリとオナガがざわめいて、ムクドリを追い払う。追われたムクドリたちはまた西の空へと羽ばたいて、それからぐるりと旋回して、そうしてまた、ヒヨドリとオナガが大声でざわめきだす。
その様子を見ていたのか、あるいは気にもとめていなかったのか、木の下のあたりの川から一羽の大きなシロサギが飛びたって、川沿いを西のほうへと飛んで、それからやはりぐるりと旋回して、東のほうへと戻ってくる。すーっと下降した白い翼は、川のへりの下へと見えなくなって、音もなく水のうえへと滑りこむ。
二羽のカモが東のほうから水平に飛んできて、真っ赤に燃えた西の空をまっすぐに見すえながら速度をあげていく。川のほうを見下ろすと、また別のカモが二羽、ゆるやかな流れに乗るようにして水の中を東のほうにすいーっと静かに進んでいく。
川と道のへりのところから何かの雑木が川に向かって生え出して、川面に小さな木陰をつくっている。水中を行く二羽のカモは夕陽に照らされた明るい水面から、その小さな雑木の影のほうへとゆっくりと後ろ足を漕いで、それからその木陰の中にすいこまれる。カモの背中で夕方の光と葉っぱの影がちらちらとゆれる。
「細長い世界だね。」
すぐ横を通りすぎていった小さな女の子が、手を引いて歩く母親のほうをむいて、そんなことを言っているのが聞こえた。

山を歩いている見知らぬひとを無闇に写真におさめることを慎もうと思う気持ちは、ふと訪ねた旅先の小さな教会の内部をカメラに写すことをためらう気持ちと、どこかとてもよく似ている。
山の上で日が暮れて、道の横になにげなくひとりのひとの影が浮かんだ。その影のあまりに純粋な形に思わずシャッターボタンを押してしまい、それから我に返り、影くらい、背中くらい許されるかな、、、とひとり悶々と苦しい言い訳を心の中にならべながらとぼとぼとテントのところに戻った。振りかえると、影はもうまっさらな夜の闇にのまれていた。

美しいへりをした山のうえで、ある本の中に書かれていた「雲のへり」という言葉を、なぜだか何度も思いだしたことがあった。雲のへり、山のへり、町のへり。「へり」という不思議な2文字の響き。
小屋の近くには小さな公園があって、さっきそこを通りかかった時、何の気なしにその公園の砂場のへりにひょいと登ってみた。砂場の周囲をぐるりと囲う、わずか15センチほどの高さのちっちゃなへり。
その細いへりの上を、どこかの山のうえの岩場か何かだと自分に言い聞かせながら、落ちないように歩いてみる。誰もいない砂場の四周をぐるりと回って、もといた場所に戻ってくる。そうして、その小さなへりの上から砂場のむこうをなんとなく眺めたとき、自分の立っている砂場と、そのむこうの1本の木と、さらにそのむこうにある水飲み場とが、ひとつの軸線の上にすーっと揃えて配列されていることに気がついた。
小さなへりの上から見える砂場と木と水飲み場だけのなにげない風景は、完璧な左右対称をなしていて、そのさまがなんだか微笑ましい。ここに木を植えたのは公園課の職員さんか、はたまた植木屋さんか。それともまったくの偶然なのか。あるいは1本の木が自らの意思でこの軸線の上を自分の居場所と決めたのか。
道のほうから子供のはしゃぐ声がして、公園をめがけて全速力で駆けてくるのが目に入る。砂場にひろげた空想を片づけて、小さなへりから地面に降りると、その正対称の幾何学はふいっと静かにどこかへ消えた。

朝、夏が少しだけ帰ってきたかのような陽気のなかを自転車で進んでいると、商店街の道の先に、大きな花束が揺れているのが目に入った。
少し腰の曲がったひとりのおじいさんが左手にもった花束を肩に担ぎ、むこうのほうへと歩いていく。肩に担がれた花束はおじいさんの背中の隣でゆらゆらと風に揺れて、古ぼけた街並みの中に鮮やかな色を咲かせている。
黒っぽい服を来たおじいさんは、スポーツシューズをはき、キャップをかぶり、黒い日傘をさしていて、腰にはポーチをさげている。たぶんそれなりに長い道のりを歩いていくつもりなのだろう。商店街を抜けて坂道をゆるやかに下っていった先には、坂の途中に大きなお寺があるから、あのお寺の中のお墓に向かって歩いていくところなのだろう。
おじいさんの横をゆっくりと自転車で追い抜く時、ちらりと手元を見ると、黒い日傘の根元をぐいと握った右手が勇ましい。男のひとが持つにはいくぶん可憐にも見えるその日傘は、あるいはもしかしたらおじいさんの持ち物ではなく、これからむかうお墓のひとがかつて持っていたものなのかもしれない。
大きな花束を抱えて、一歩一歩前へと進んでいくおじいさんの姿を背中に感じながら、自転車は坂道へとさしかかる。坂のところのお寺の境内では、大きなケヤキの木に何匹かのセミがしがみついて、最後の声を振り絞り、夏の余韻をギリギリのところで醸し出している。おじいさんが手を合わせた時、まだそこで彼らが鳴いていると良いなと思う。
それから自転車は坂道をくだりきり、橋を渡って蕎麦屋さんの前を通りすぎていく。ふと道ばたに目をやると、蕎麦屋さんの脇の小さな通路のところに、ビニールひもでふわっと束ねられた彼岸花が、花盛りをすぎてもなお太陽のほうを見上げ、じっと静かにその場に佇んでいるのが見えた。耳の奥でセミの声がした。

「てっぺんへ出ると、私は素晴らしく大きくなった。山のように大きくなった。」
今にも押しつぶされてしまいそうなほどに重たい日々の暮らしを、淡々と短い言葉で刻みつづけたある古い女性の詩人の、その言葉の片隅に、ほんの時たまふわっと幻のようにたちあらわれてくる山のイメージは、たぶんそのひとの過ごした低い低い毎日の、その低さのぶんだけ高くて大きなものになるのだろう、
自転車に乗って小屋に来る道すがら、そんなことを茫々と考えた。
そのひとの詩のなかに存在する山は、地べたを這うような凡庸な毎日があってこその山なのであって、そのような日々のないところに、きっとあの山はないのだ。
